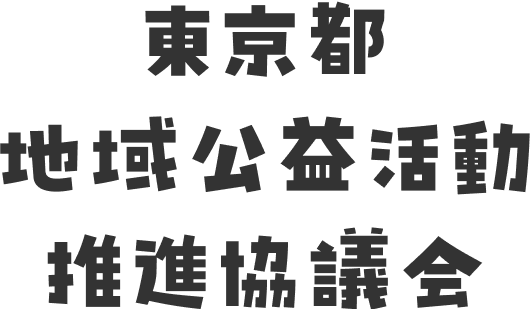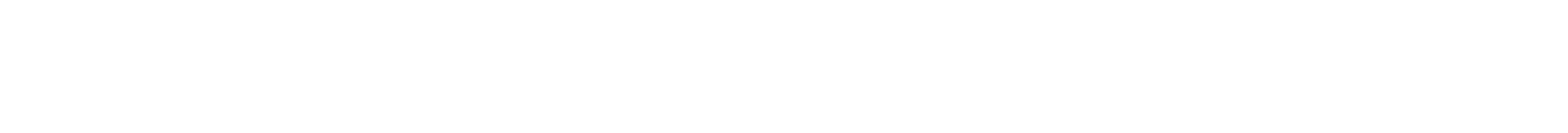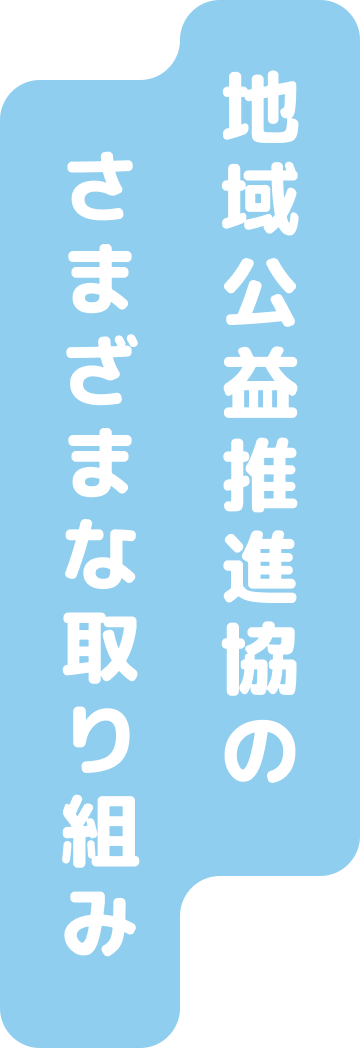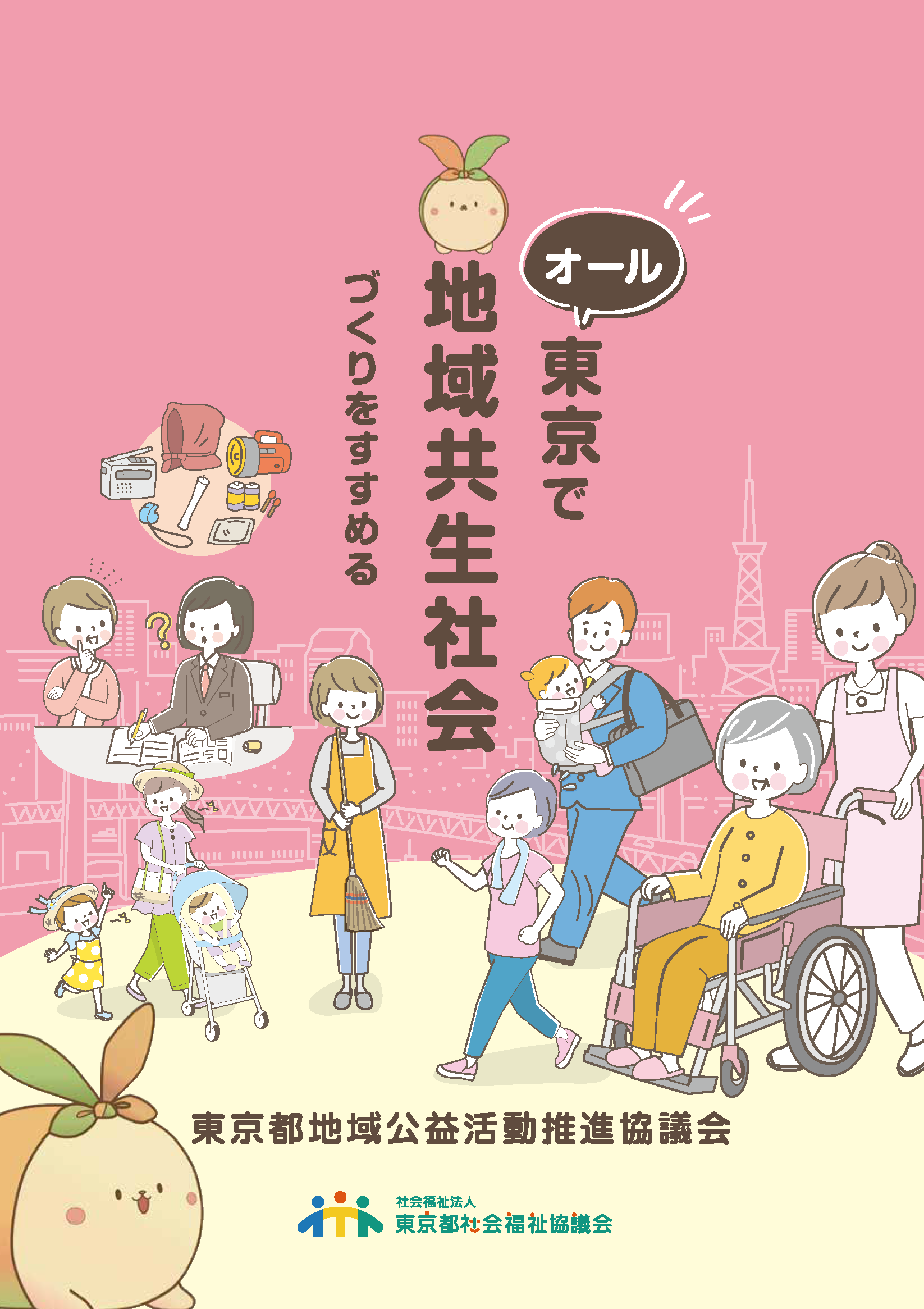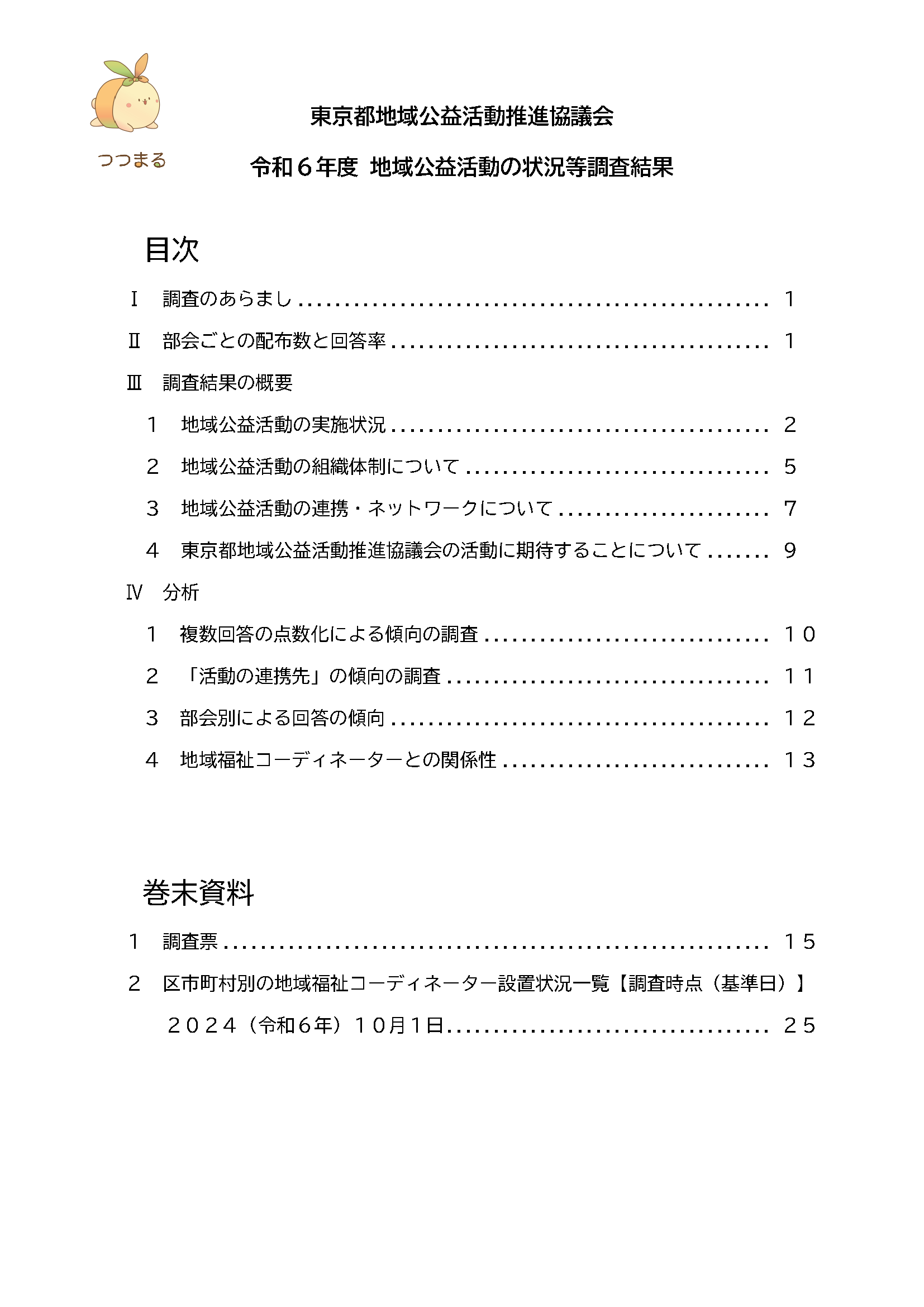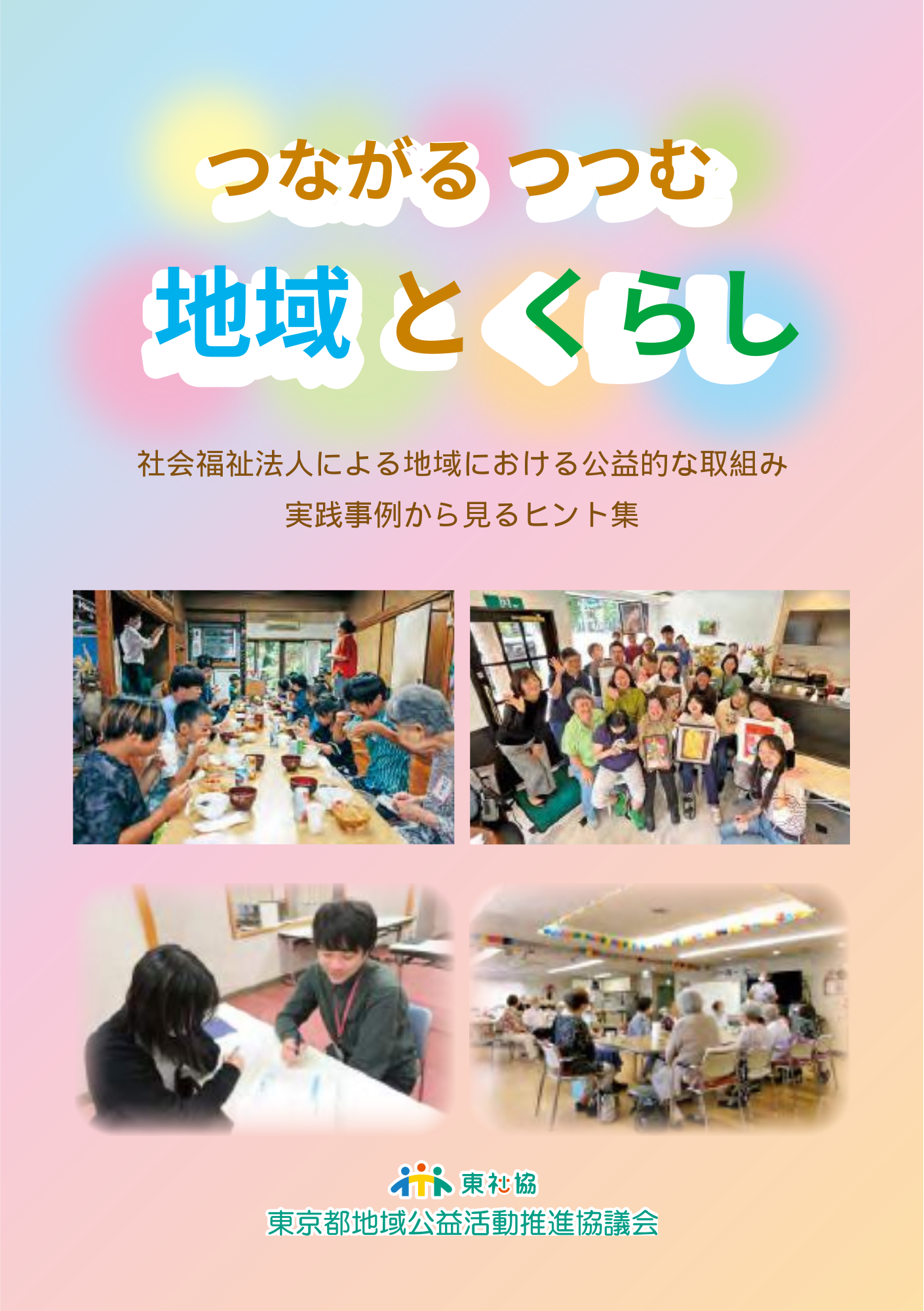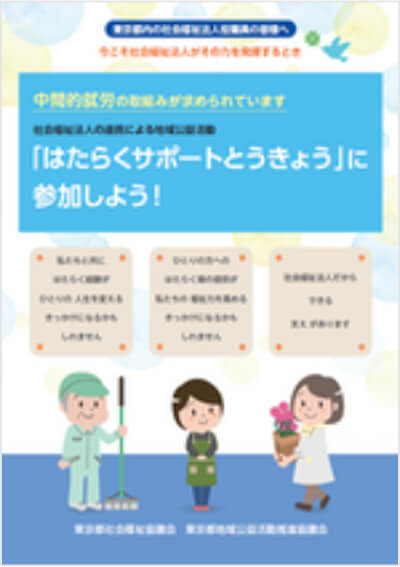社会福祉法人 まりも会 清瀬喜望園
清瀬市
社会福祉法人まりも会 清瀬喜望園は令和7年4月1日に開設した新しい施設にて、身体障害者の方の通所生活介護、ショートステイ等を行っています。無料で利用できる「まりもホール」や、ブックカフェのような誰でも気軽に過ごせる空間「きままにルーム」が開放されており、地域の方が施設を訪問するしかけが各所に設けられています。
地域住民、そして施設利用者を巻き込みながら地域公益活動を進める清瀬喜望園の取組みを取材しました。
新しい出会い、新しい交流 「地域の方の想いを実現するような地域の宝物に」
---施設がオープンされて約3か月経ちます。地域の方々からの反応はいかがでしょうか
近隣のNPOや住民の方などから、ホールの貸出しの問い合わせ次々に来ています。6月に推進協議会のホームページに寄稿をしたのですが、それを見たといった反響は大きかったですね。
清瀬市内の社会福祉法人からも、推進協議会のホームページ見たよという声をいただくことが多かったので、投稿してよかったなと思っています。
新しい施設だから周知されるのに1年くらいかかると言われていたのですが、3か月でもかなりの問い合わせがあります。ホールや交流スペースなど、無償で貸し出しているということが大きいのではと思います。
地域に向けて開放している空間「きままにルーム」 「まりもホール」運動だけでなく、研修会なども実施可能
---推進協議会のホームページには音楽療法の取組みをご寄稿いただきました。そのほかにはどのような取組みが進んでいますか
男性向けの料理教室や、子供向けの支援を中心に施設を利用してもらっています。そういった地域での取組みに参加された人が、今度は個人で新しく地域のための取組みを始めたいといった声を挙げてくれるようになってきました。先日も、何度か音楽療法に参加している方が、自身のコーラスグループ発表会をしたいとご相談してくださいました。
喜望園で行っているイベントや活動に参加された方が、次々に別の活動の担い手となってくださっています。
清瀬喜望園のコンセプトとして「新しい出会いから新しい交流の創出」を掲げています。喜望園が地域の方の想いを実現するような地域の宝物になっているといいなと思います
支援の在り方を見つめなおす。「地域に施設を開くことで色々な情報が入ってくる」
---利用者の生活に変化はありましたか
利用者は地域の人と交流するといった新しいことが大好きなんですよ。今日も午前中に大学生が施設を見学していたのですが、フロアにあるピアノを弾いてもらうと利用者が居室から出てきて喜んでいました。地域とのつながりが増えてきたことで、利用者の生活に幅が出てきたのではないかと思っています。
地域の人が施設を訪れて、施設や地域の中であれこれしたいという思いが生まれることで、地域と施設の関係性ができていくことが理想ですね。居住棟も交流スペースとつながっているので、将来的には地域の方がそこまで入ってもらってきても構わないと思っています。施設も利用者もそういう経験を蓄積していくことも非常に大切だと思います。
地域の人たちが入ってくださることで、利用者への支援の選択肢が増えていく。施設が地域の停留所となり、人が自然に行き来する場であってほしいです。利用者さんの生活を豊かにしたいというのが職員共通の想いですね。これまでも試行錯誤し、新しい支援の形を作っていくことをイメージしながら施設をデザインしてきました。変化に柔軟に対応できるようになることを目指していきます。

---公益的な取組みを続ける中で、施設の業務や職員に変化はありましたか
近隣に大学があるので、ボランティアをしたいといった問い合わせが増えています。そのボランティア活動がきっかけで、当法人への就職につながっていたりということもあります。それから、建物ができる前、仮設施設の段階(オープン前は敷地内の仮設施設にて事業を運営)から地域との交流事業が始まってきたのですが、そのころから職員の離職率はすごく下がったかなと思っています。

清瀬喜望園の目指す施設とは
---今後地域公益活動を進めていく中で、どのようなことに取り組んでいきたいですか
施設内の交流スペースと利用者の生活スペースをつなげているのは、地域の方にもっとかかわってもらいたいからなんです。施設の敷地内でもベンチや東屋に寄ってもらうとか、最初はそんなことでもいいかなと思ってます。日常の中に施設が溶け込んでいくことが理想です。将来的には、喜望園に来れば何かやっているなと地域の方に思ってもらって、そこには必ず利用者も参加していると認識されることが最終的な目標です。
障害者施設も、例えば20年後にどのような形になっているかわかりません。将来的にいろいろな可能性を残すような形で施設をデザインしてきました。絶えず職員に向けて、将来のことを考える、そういったメッセージを発していくことが経営層としては大事かと思います

清瀬喜望園の皆様
-
障害者施設を地域に開くためには(福)まりも会 清瀬喜望園 (まりもタウンフェスティバル)
2026.01.26
-
実践発表会 2025 Part 2(福)恩賜財団東京都同胞援護会 自立ホームいこい 「地域のプラットホームとしての役割」
2026.01.09
-
実践発表会 2025 Part 2(福)大和会 特別養護老人ホーム 新宿和光園 「地域になくてはならないダイバーシティ施設を目指して」
2026.01.09
-
実践発表会 2025 Part 2(福)池上長寿園 大田区若年性認知症支援相談窓口(福)東京コロニー 東京都大田福祉工場「誰もが表現できる場づくりの実践」
2026.01.09